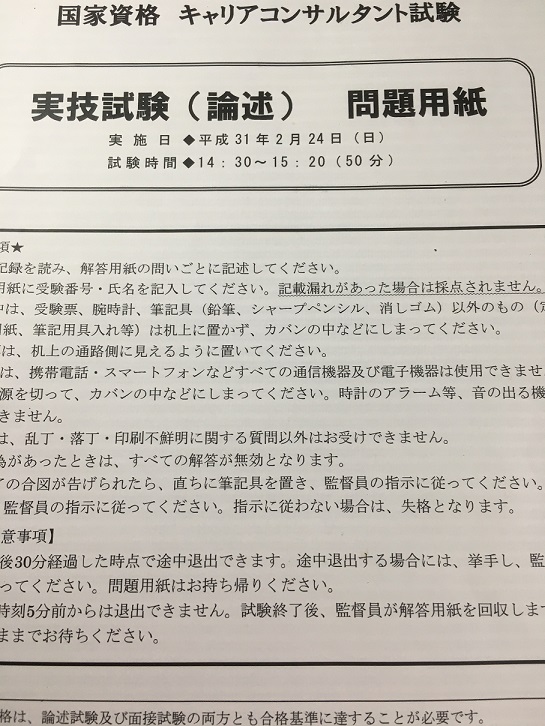久々に、国家資格キャリアコンサルタント試験について書きます。
今回は、実技論述試験についてです。次回(第15回)は11月1日(日)が試験日ですね。JCDA,協議会とも試験実施に向けてコロナ対策を考えて実施されると思いますが、再度延期にならないとよいですね。では本題に移ります。
どちらの団体で受ける?

ご存じのとおり、国家資格キャリアコンサルタント試験の実施団体は2つあります。
1つは、JCDA(日本キャリア開発協会) もう1つはキャリアコンサルタント協議会
受験申請時にどちらで受験するか?決めることになりますが、両団体で「実技論述試験」と「実技面接試験」の内容や評価のポイントが違うので、そこを考慮に入れて受験団体を決める必要があります(学科試験は両団体とも同一問題です)。
私は試験実施団体をJCDAにしました。理由は以下の通りです。
・実技論述試験問題が自分にとっては協議会の問題よりも回答しやすかった。
・実技面接試験後の口頭試問の内容が、自分の答えやすい内容だった。
実技論述試験のテキスト
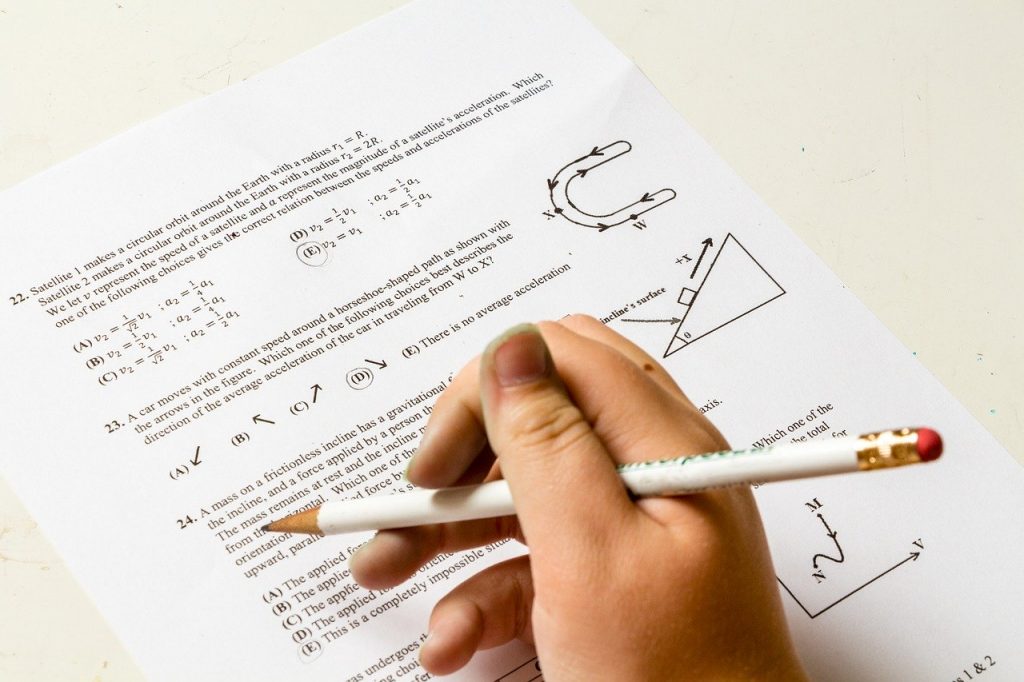
私が受験した頃は、論述試験に関するテキストが発行されておらず、ネットにUPされている3回分の過去問だけが頼りでしたが、今はこんなテキストがあるのですね。
もちろん上記のテキストに頼らず、キャリアコンサルタントの予備校でも「論述試験対策講座」なるものが用意されていますが、結構すぐに「満員御礼!」になりますので、予約はお早めに!です。
私は結局論述対策や面接対策の講座を受けられず、また国家キャリコン用のテキストも無いまま本番をむかえてしまいましたが、上記の2級用のテキストがあったので、こちらで事例を読んで回答する対策もしていました。
過去問も含め、論述対策については下記を意識して行っていました。
・とにかく、多くの事例に接する
・試験時間が短いので、短時間で事例を理解し、今後の展開を考える練習をする
・JCDA(協議会で受ける人は協議会)の出題のクセに慣れておく
実技論述試験は50分という試験時間ですが、とてつもなく短く感じます。
たぶんかなり優秀な人以外は時間内にようやく書き終わるくらいで、見直しも充分できないまま終了、って人がほとんどでしょう。なので問題として出された事例を如何に効率よく読み、瞬時に内容を把握し、CL(クライアント)が抱えている問題をどうやって解消していくかを考える練習(対策)を積んでいくことが必要になります。
では次に、JCDAと協議会の問題についての特色を見ていきましょう
JCDAと評議会の論述試験問題について
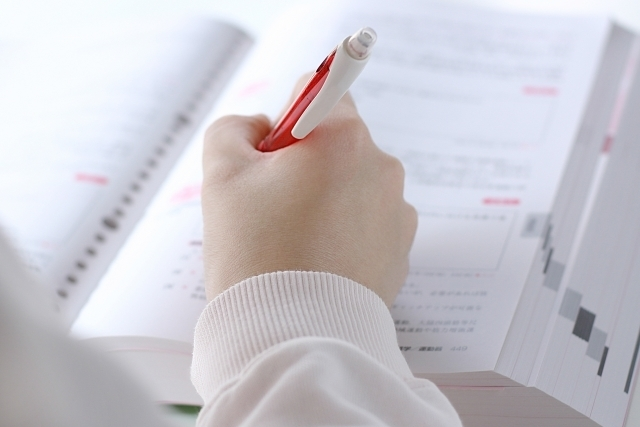
実技論述試験は、JCDA、協議会ともに逐語録を読んで、問いに答えていくスタイルですが、根本的に違うことがあります。
JCDA
事例が2パターンあり、2パターンを比較したうえで問題点の把握と今後の展開を考えさせる出題となっている。
協議会
事例は1パターン。CLの主訴と問題点の把握、そして今後の展開を考えさせる出題となっている。
以上が、大きく違うので私としては、どちらが自分にとって回答しやすいのか?次第で受験団体を決めてもよいのでは?と考えています(もちろん、実技面接試験での評価の観点も両団体で違うので、そちらも含めて考える必要はありますが)。
JCDAの論述試験について

ではここから、私が受けたJCDAの実技論述問題について触れていきましょう。
まず、前段でどんなCL(クライアント)でどんなCC(キャリアコンサルタント)なのか?の説明があり、2つの事例の前提となる共通部分が提示されます。その次に【事例Ⅰ】【事例Ⅱ】に分かれる形となります。
問い1
事例ⅠのCCと事例ⅡのCCとではCLに対する対応の仕方が違っており、どんな違いがあるのか?を指定された5つの語句を使用して記述させる問題です。
結構回答するのに時間がかかる問題でして、この問題を最初に時間かけて考えちゃうと他の問題にかける時間が無くなるので、私は問い1の回答を後回しにしてました。
さて、他の簡単な問題を片付けた後にこの問題に戻ってくるのですが、解き方として実践したのが、5つの語句それぞれで共通する部分を事例の中から探し出し、語句を使って短文を作ることで攻略したことでした。
例えば「内省」という語句であれば、CLが内省している箇所を探したり、「ものの見方」という語句であれば、CLが間違ったものの見方をしている箇所や、逆にCCの関わりによってものの見方が変わったりした箇所はあるか?を探して紐付けし、短文を作るのです。
そして、それぞれの短文が出来上がったら、事例Ⅰ、Ⅱの違いを一文で表すことができるように繋いでいく、という方法をとっていました。
短文を作らずに、最初から回答を考えちゃうと、結構時間がかかったり、それぞれの語句の使い方を間違えて、もう一度書き直したり、があるので短文作って繋げていくことが一番効率よく、的確に回答文を記述できると考えています。
問い2
事例Ⅰ、Ⅱの中でCCが発した応答が下線で指定されており、その指定部分のCCの対応は「相応しいか」「相応しくないか」をチェックさせ、その理由を記述させる問題です。
私はこの「問い2」をまず最初に回答してました。両方の事例は明確に良し悪しが分かるものなので、一番とっつきやすく感じてました。ただ、理由に関しては安易に回答してはいけません。できればCCの対応に対してCLが発言した内容をキーワードにして理由を書いていくとよいと考えています。結局CCの対応でCLの発言が変わるわけですから、良い方向に進んでいるか?悪い方向に進んでいるか?はCLの発言で分かることが多いです。
問い3
CLの問題点を記述させる問題です。
ここで気をつけたいのが、「問題点」と「主訴」は意味が違うということです。問題点を書けと言われているのに主訴を書いてはいけません。結構混同しちゃう場合があるので気をつける必要があります。
そして、多くのCLは「ある種の思い込み」と「情報不足」から悩みを抱えているケースが多い(視野狭窄に陥っている)ので、CLがどんな思い込みをしているのか?CLは視野狭窄に陥っていないか?を考えていくと問題点が把握しやすいのでは?と思います。
また、CLが知らないことを知ることで、展開する可能性があることも考えておくと、次の問いのヒントにもなります。
問い4
事例Ⅱ(CCの対応が良いほうの事例)でのやりとりについて、あなたなら今後どのようなやりとりを面談で展開するか、具体的に記述せよ、という問題です。
ここで気をつけたいのが、この事例にあるCLのためだけの!具体的な方法を考えることが必要である、ということです。誰にでも当て嵌まる抽象的な表現ではダメです。
やはり事例に則して、CLに役立つ情報を入れていくとか、「こんな気づきをこんな方法で促していきたい」といった具体的な方法を記述することが必要と考えます。
また、すべての問いへの回答に言えることですが、私たちは「キャリアコンサルタント」という専門家になることを目指して受験しています。ですから、回答にもなるべくキャリアのテキストに出てくるような「専門用語」を使用すると良いかと思います。
まとめ
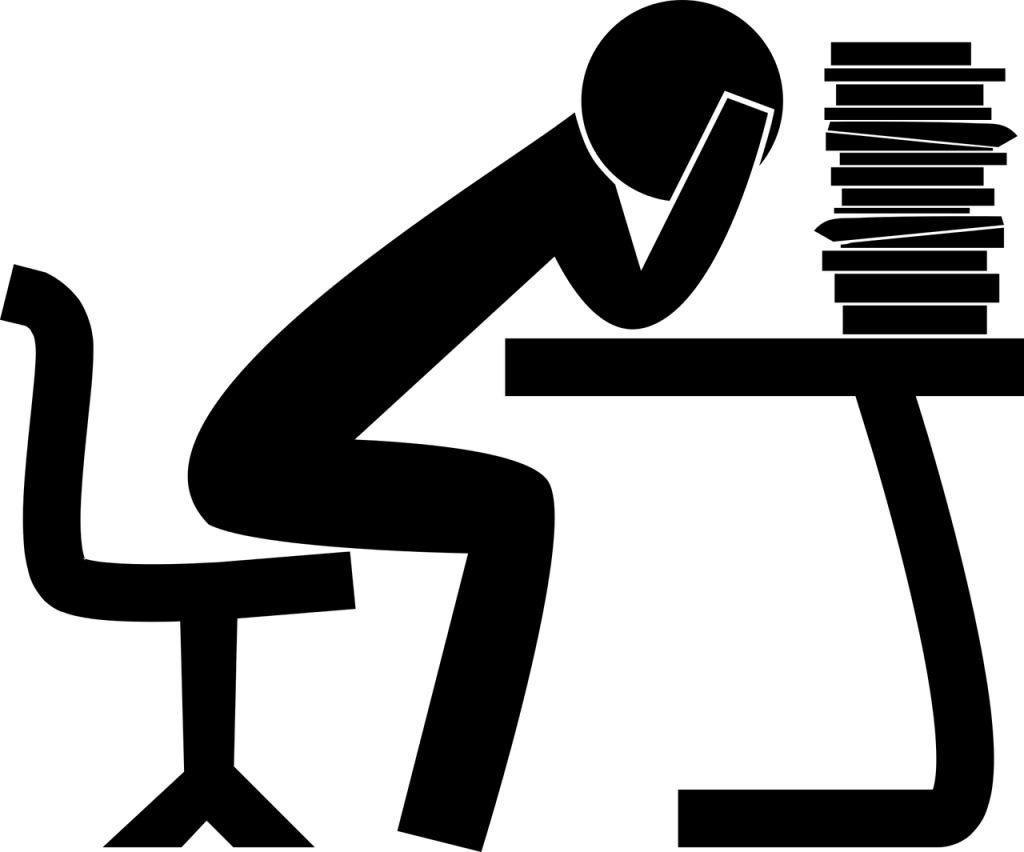
以上がJCDAの実技論述試験において、私が実践した方法になります。
とにかく、試験時間が短いのが一番のネックで、如何に短時間で事例を理解し、CLが持つ問題点を把握し、自身でそのCLに対して今後どうカウンセリングするか?を考えながら、設問に答えていくことが必要なので大変だとは思います。
とにかく今は、テキストも各種発行されていますので、当ブログでお話した以上の解説がテキストに書かれていると思いますので、論述試験対策のためにぜひ購入を検討してください。
なるべく多くの事例に接し、正しい解釈をしながら短時間で問題についての回答を記述する力を付けることが一番の対策になります。
今日は、キャリコン試験の実技論述試験についてでした。
参考になりましたら幸いです。
【気になる資格がみつかるサイト・資格Hacks】